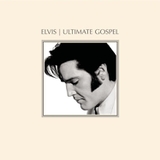旅の終わりのたからもののレビュー・感想・評価
全12件を表示
民族のルーツを知ることで、自身の中にあるDNAが覚醒していくのかな、と感じた
2026.1.20 字幕 アップリンク京都
2024年のドイツ&ポーランド合作の映画(112分、G)
原作はリリー・ブレッドの自伝『Too Many Men』
ホロコーストを生き延びた父と共に故郷を旅する娘を描いたヒューマンドラマ
監督はユリア・フォン・ハインツ
脚本はユリア・フォン・ハインツ&ジョン・クエスター
原題の『Treasure』は「宝物」という意味
物語の舞台は、1991年のポーランド・ワルシャワ
ニューヨーク在住の音楽ライターのルーシー(レナ・ダナム)は自身のルーツを知るために、ホロコーストを生き延びた父エデク(スティーヴン・フライ)と共に、オケンチェ空港で待ち合わせをしていた
約束の時間に来なかった父は、呑気に買い物をして乗り遅れたと言い、その後も自由奔放な行動を繰り返していた
ルーシーはあらかじめ旅のプランを立てていたが、父はその場所には行きたがらず、観光地などを巡ろうとしていた
それでも、ルーシーは頑なに生家に行きたいと言い、父は仕方なく、そこに彼女を連れていくことになったのである
映画は、2歳の時に国外に脱出したルーシーが、自身のルーツを探るために両親が生まれ育った地に行くというもので、1年前に母親が他界したことが告げられていた
父にとっては忌まわしい過去であり、避けたいところもあったと思うが、娘1人で行かせるわけにもいかず、やむを得ずに付いてきたという感じになっていた
ユダヤ人が地元に帰ってきて襲われるという事件が過去にもあって、それゆえに足を踏み入れるのは危険だという認識があった
だが、ルーシーも自分がユダヤ人であることを知り、その過去を紐解いていく中で、ホロコーストに関しては避けて通れない命題となっていた
あの時何が起こっていたのか
それを知るためには、現地に赴くしかない
そして、民族の存続の転機となった場所を訪れることで、自身の中にある「欠けたピース」を嵌めようと考えていたのである
映画は、父と娘のロードムービーとなっていて、バツイチのルーシーへの当たりはやや強めで、ルーシー自身がキャリアのために離婚をしたことが明かされていた
父親の精神状態も不安定だったようで、セラピーを受けたがらないのに娘の分析はすると言われていて、戦争時のトラウマというものは時折顔を出してしまうのだろう
彼にとって、生死を分けたアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所へ赴くという行為は、その場所が観光地化していても躊躇いを感じる場所だった
あの時五感を割いた匂い、風景などが想起される可能性は高かったのだが、どうやら匂いに関しては感じなくなっていた
だが、歴史として残っていることと真相のズレなどが生じていて、そう言ったものが現地で蘇ってくるという内容になっていて、父親の中で肥大化しすぎたイメージが徐々に等身大になっていく様子も描かれていたのではないだろうか
いずれにせよ、父と娘の間にある決定的なものは埋めようがないのだが、そんな欠片探しの中で思わぬサプライズがあった、という結末になっていた
あれをどうしたのかまでは描かれないが、2人は二度とあの土地には戻らないと思うので、放棄もしくは現状維持のまま、ということなんだと思った
映画のタイトルは『Treasure』で、単語の意味としては「宝物」というものだが、劇中ではタクシードライバーのステファン(ズビグニエフ・ザマホフスキ)のセリフとして登場し、翻訳では「光栄でした」というものになっていた
これは、ホロコーストの過去を持ちながらも、娘のために逃げなかったエデクへの賛辞であり、その勇敢な行動が自身の人生を変えていく様子を見てきたからだと思う
そんな父は現地でちゃっかりと女性をゲットしていたりするのだが、双方ともに果てないのはすごいなあと思ってしまった
旅先でありながら自らにタトゥーを刻む癖はだいぶヤバい
ニューヨークで生まれ育ったルーシーは、ジャーナリストとして成功しているが、どこか満たされない想いを抱えていた。その心の穴を埋めるため自身のルーツを探そうと、父エデクの故郷ポーランドへと初めて旅立つ。ホロコーストを生き延び、その後決して祖国へ戻ろうとしなかった父も一緒だ。ところが、同行したエデクは娘の計画を妨害して自由気ままに振る舞い、ルーシーは爆発寸前。かつて家族が住んでいた家を訪ねても、父と娘の気持ちはすれ違うばかり。互いを理解できないままアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所を訪れた時、父の口から初めて、そこであった辛く痛ましい家族の記憶が語られるが──(公式サイトより)。
娘のルーシーは1991年で36歳、東西冷戦が終結し、湾岸戦争に突入した、ある意味でイケイケのアメリカ・ニューヨークでジャーナリストという花形職に就くが、人生がどうにも思うに任せない一方で、父エデクはホロコーストでの凄惨なトラウマを抱えながらも奔放で楽観的で毎日が楽しそうである。この対比的な構造の中で、物語を生むのが、「母の死」というきっかけと、こうした生い立ちに時代性を加えた「感覚」のズレである。
例えば、ルーシーは、両親の住んでいたアパートメントや経営していた工場や食器に自分のルーツの欠片を見出そうとするが、父はそんなものはただのモノだと一蹴する。かつての壮絶な過去を思い出してしまうスイッチになり得るのはもちろんだが、同様に本当に「ただのモノ」だと思っている風でもある。
父のエデクは幸せな結婚や家族観はもとより、恋愛観やセックスに至るまで、「普通」という固定観念を、旅程につきまとうおばさん集団の応援を受けつつ、ルーシーに強要する。アウシュビッツによって「普通」を壊された過去があるという前提は理解しながらも、その無理強いは親子とはいえ一線を越えており、ずいぶんとデリカシーに欠く。
ルーシーはルーシーで、ポーランドにまでシリアルを持参するレベルのベジタリアン(偏食家)であるが、それがダイエット目的なのか、何か思想的な背景を持つのか、あるいは個人的なトラウマなのか、最後まで明示はされない。ストレスを感じると、旅先でありながら自らにタトゥーを刻む癖もだいぶヤバい。大きなルーシーがバスタブに浸かって、虚空を眺めるシーンは本作の白眉であろう。
このへんてこで凸凹な感覚のズレが解消されないまま進めるの親子には、たとえ「負の遺産」と世界から忌避されるような場所であろうとも、出生の地という共通のルーツがある。本作はその確認の旅路であった。
幻想を追って苦しむ娘と、現実から目を背けていた父のロード・ムービー
ホロコーストの生存者が抱える記憶を扱った映画はいつも観る者の胸を苦しくさせる。
本作は、その記憶が生存者だけでなくポーランドの地を踏んだこともないアメリカ生まれの娘に迄引き継がれていることを通して、想像を絶する心の傷を浮き彫りにします。
おおらかに人生を愉しんでいるかに見える父親が直視しようとしていなかった現実と、娘がそれとは気付かずに抱えていた罪悪感の正体が旅を通して二人の目に映し出されます。
現実から目を背けていた父が、旅の終わりに娘に手渡したたからものとは…
悲しい思い出とどう折り合いをつけて生きてゆくのか。
戦後75年。
第二次世界大戦の記憶を持つ世代が世を去りつつある今日こそ、人類が犯した大いなる過ちの記憶が世代を越えて受け継がれてゆくことを願ってなりません。
ポーランドの厳しい現実を含めて、多くの記憶を映画を通して受取った気がします。
運転手、ステファンとホテルマン、タデウスのキャラに萌え萌えです(笑)
思い出したくない思い出もある
娘はもう少しお父さんから学びなさい
過去は忘れたい父とその過去をちゃんと知りたい娘のチグハグ親子のロードムービー
ホロコーストを生き抜きNYに拠点を移して人生を謳歌する父・エデク、過去を語らない父の背を見て育った娘・ルーシーのロードムービー
過去を話してもらえないことで、自分の人生に欠けた何かを感じるルーシーは、ポーランドへの旅を強行する。彼女を突き動かすのは父の、家族の軌跡を知りたいという衝動。それが父にとっては忘れてしまいたい過去であってもだ。
特にルーシーが旅の途中でありふれたティーセットに執着する様はとても共感できた。
私も一昨年に他界した祖父が使っていた酒器を形見にもらい大切にしているからだ。ブランド物でもないありふれた酒器である。でも、私には祖父が愛用していた世界でたった1つの酒器なのだ。
辛すぎた過去だから目を背けたい父をよそに、ルーシーはひたすら過去に踏み入る。その強引さは父の気持ちを顧みることがなかったが、旅を続けるうちに次第に父の過去ではなく、父の気持ちにも目を向けるようになる。
自分自身のために過去を知りたかったルーシーが旅の終わりに手に入れたのは、過去の事実だけではなく、父との絆。過去を隠すことでどこか距離を感じていた父への気持ちの変化、それこそがルーシーが手に入れたたからものなのだ。
【忘却という名の防衛、沈黙という名の遺産。1991年ポーランド、錆びた標識の裏側に宿る真実】
1991年という歴史の停滞期を、これほどまでに映画的な「沈黙」と「質感」で捉えた作品は稀有である。
本作『旅の終わりのたからもの』が提示するのは、ホロコーストという巨大な「不在」を巡る、痛烈なまでの肉体的な対話である。1991年のポーランド。鉄のカーテンが崩壊し、資本主義の濁流が歴史を上書きしようとする不安定な時空。この「過去がまだ生々しく腐敗している時代」の空気を、ユリア・フォン・ハインツ監督は彩度を削ぎ落とした寂れたトーンで完璧に醸成した。
特筆すべきは、言語的説明を排し、画(フレーム)そのものに物語を独白させる映画的演出の強度だ。アウシュヴィッツの引きのショット。等間隔に並ぶ焼却炉の残骸は、そこにかつて漂ったであろう醜悪な臭いすら消去された「無菌状態の地獄」として、その設計思想の異常性を網膜に焼き付ける。エデク(スティーヴン・フライ)が、現在の観光地化した「博物館」という呼称を拒絶し、「収容所」と言い直す瞬間の断絶。それは、歴史を安全な記号として去勢しようとする現代社会への痛烈な告発だ。
父娘の断絶は、そのまま「生存のための忘却」と「自己確立のための記録」の衝突である。娘ルーシー(レナ・ダナム)がホテルのレストランで頑なに「鳥のエサ」のような食事を摂り続ける姿。それは、父が経験した「欠落」を自らの肉体に刻もうとする、未体験世代の悲痛なコンプレックスの表出だ。中盤、彼女がバスタブに浸かり、自らに課した「禁欲」を破ってチョコを貪るショット。バスタブを浸食するスライムのように膨張した彼女の肉体は、精神論では解決し得ないトラウマの重力を象徴し、本作でもっとも官能的かつ残酷な映画的瞬間を形成している。
劇中で父から手渡される『失った腕のアリバイ』。それは、失われたものへの「幻肢痛」を抱えて生きる者たちの物語だ。エデクが娘に投げかける「パンプキン」という愛称。その滑稽な響きの裏に、彼が一生をかけて封印しようとした「最も愛し、最も傷ついた記憶の残影」が重なる瞬間、観客はこれまでの父娘の不毛な攻防のすべてが、痛切な鎮魂歌であったことを知る。
ラスト、空港へ向かう黄色いタクシーが遠ざかる中、画面中央に屹立する「錆びた標識の裏側」。何も描かれず、ただ風化していくその鉄板の質感こそが、エデクが抱え続けた沈黙であり、アウシュヴィッツの虚無であり、そして私たちが受け継ぐべき「答えのない歴史」そのものである。サバイバー特権でゴーカートに興じるという、滑稽でいて救いようのない現実の皮肉すらも、エンディングの旋律とともに「逃れられぬ影」として我々の足元に縫い付けられる。本作を観ることは、歴史を学ぶことではない。歴史という名の「錆びた鉄板」に、自らの指先を触れさせる儀式である。
X:物語の臨界を穿つ者|映画観測官(@kinemalover)
試写会初体験でしたが…
自分が普段観るタイプの映画ではないのですが、たまたま試写会に当選したので鑑賞しました。
"娘と父"がルーツを辿るロードムービーで、いいところもありつつ、やっぱり自分には合わないなぁ…というのが素直な感想です。
ストーリーにあまり興味が出ず、映像も自分が一番嫌いなPOVや人物の視点以外でカメラがブレるシーンが時々入ってしんどい…
エデクが旅で出会った二人組の女性の片方とベッドインしたことが分かった翌朝にルーシーが帰るって言い出した後に、もう一人の女性の方にタバコを渡されるシーンでは火を付ける描写が無くて、火が付いているシーンになっていてカットがチグハグに感じました。
これが吸い終わりとか火を消すところなら時間経過を感じて行間があることが分かるのにと思いました。
またルーシーが祖父のコートを渡してエデクが衝撃を受けるシーンは良かったけど、あのコートを手に入れる前までずっとコートが要るって言ってたのにすぐ渡さないのがこのシーンのために後回しにしたとしか思えなくて納得感がすごく薄いです。
最後になんの伏線や匂わせもなく土地の権利書が出てくるのも唐突だし、話作りもカットも雑に感じるところが多くて残念でした。
Pumpkin
初のキノシネマの劇場での試写会にて鑑賞。
設備も良いですし料金もお得で観れるんですがいかんせん劇場が少ないもんで久々に行ってきました。
あらすじ未読だったので本編前のトークショーでサクッとあらすじを聞き、ホロコーストの生き残りである父と自分のルーツを知りたい娘の旅という事でロードムービー的なものを期待したのですが、んーこれは中々クセの強い一本でした。
父と娘の心情が最初はぼかされており、話が進んでいくごとに2人がなぜすれ違ってしまうのかというのが明らかになるのですが、そこに行くまでの行動が身勝手&失礼&思想強めといったやつなので、フラストレーションが溜まる作りになっていました。
娘のルーシーはどこかせっかち、そして面白いくらい礼儀がなっていないので、他人の家を訪問してもお邪魔しますと一言もなくズカズカ入っていく様子は中々に嫌な奴でした。
父親のエデクはいわゆるノンデリパパで、自由すぎるが故にルーシーや周りの人を振り回しますし、勢いも手伝って知り合ったばかりの人とエッチしちゃったりも奔放すぎました。
チップを多く払えばホテルの部屋をいじったり、交渉がうまく行ったりと、かなり一辺倒に思えてしまったのは残念でした。
エデクが元々住んでいた家に凸して、その家にある思い出の品を買い占めるとかいうどこのバラエティやねんっていう事もやるんですが、これが面白みには繋がらず、ただただルーシーの嫌な部分が出ているだけになってるのも勿体なかったです。
終盤はお互いがお互いのことを分かってなかったというのも明かされつつ、そんでもって揉め事も起こったりするんですが、なぁなぁで揉め事が解決したり、ガッツリ人の土地をあさり出したりするので、感動的なシーンのはずなのに全然感動できないのがう〜んって感じでした。
運転手は最高だっただけに惜しかったです。
製作側が入れたかったのか分かりませんが、ルーシーの下着姿だったり、入浴シーンだったりお風呂上がりだったりが映されるんですが、レナさんには申し訳ないんですが体がダルっダルやないかいというツッコミしか出なかったです。
と思ったらレナさんも製作に入っているので、全世界にお届けしたかったんやろなぁと。
やっぱスレンダーが好きです。
好みからは逸れてしまいましたが、自分のルーツを探すために関係性を取り戻そうとするという視点は面白かったですし、2人の関係性が雪解けしていったラストは観れるようになったので、近しい経験がある人ほど突き刺さるんじゃないかなと思いました。
鑑賞日 1/8
鑑賞時間 19:00〜20:52
過去と向き合う
虐げられるということは
前トークショー付きの試写会で観させていただきました。ネタバレ回避しながらも“為になる”内容はとても有り難かったです。より映画を愉しめたのは間違いありません。
父エデクの自由奔放な行動にクスッとなりつつも垣間見る思慮深い表情やはぐらかすような言葉…フックになるポイントが、物語後半のルーシーの感情の揺れ動きにリンクして「あの時の表情は…そういうことかも」と腑に落ちる。何箇所か自然に散りばめられていてこの構成の感じ良いな好きだなと思いました。
この父娘の虐げられた体験は歴史的背景をみても私の想像力ではこと足りないとは思いますが、昨年観た「リアル•ペイン 心の旅」を観たあとにも生まれた虚無感や喪失感との付き合い方(向き合い方?)は再度、自分の中で課題となった。ルーシーのようにルーツを辿ることで心のパーツは埋まってゆくのだろうか。
身内が他界した時、戸籍謄本を読みながら自分が今ここにいる不思議に思いを馳せたことも思い出した。
帰りにポスターを見て「たからもの」の5文字が棒線でつながれているデザインなのを眺めながら旅の道筋を諦めずに繋いで行ったからこそみつけたもの(人との出逢い、ルーツの品々や家族の想い)色々がたからものだったなと優しい気持ちになれました。
不完全な家族に注がれる「恵み」のロードムービー
ホロコーストという重いテーマだが、本作はスティーヴン・フライ演じる父エデクの陽気で、時におせっかいで、コミカルな振る舞いによって、絶えず「笑い」と「温かさ」に包まれている。エデクには、悲劇を悲劇としてのみ描かずに「それでも人生は続く」という強烈な肯定感が貫かれている。レナ・ダナム演じる娘のルーシーは、自分のルーツを知るため、厳粛で完璧な旅にしたいと計画していたが、父エデクはそれを極力避けようとする。この「過去を掘り起こしたい娘(第二世代)」と「過去に蓋をして今を生きたい父(サバイバー)」の温度差が物語の核になっている。
また、このちぐはくで不完全な父娘のロードムービーというシチュエーションが、ホロコーストの歴史を抽象的な「悲劇」としてではなく、ポスト生存者時代に生きる私たちに「現在進行形の課題」として引き寄せている。本作の原題“Treasure”が「たからもの」とひらがな表記されていることで、ポーランドの土の中に埋められた金品ではなく、世代間の対話を通じてようやく見出された「理解」と「和解」という恵み、そして記憶を未来へ繋ぐという「覚悟」そのものを指しているようにも想えて印象深い。
全12件を表示